共分散構造分析 ―生成AIとの協働による問題解決編―
豊田 秀樹 編著
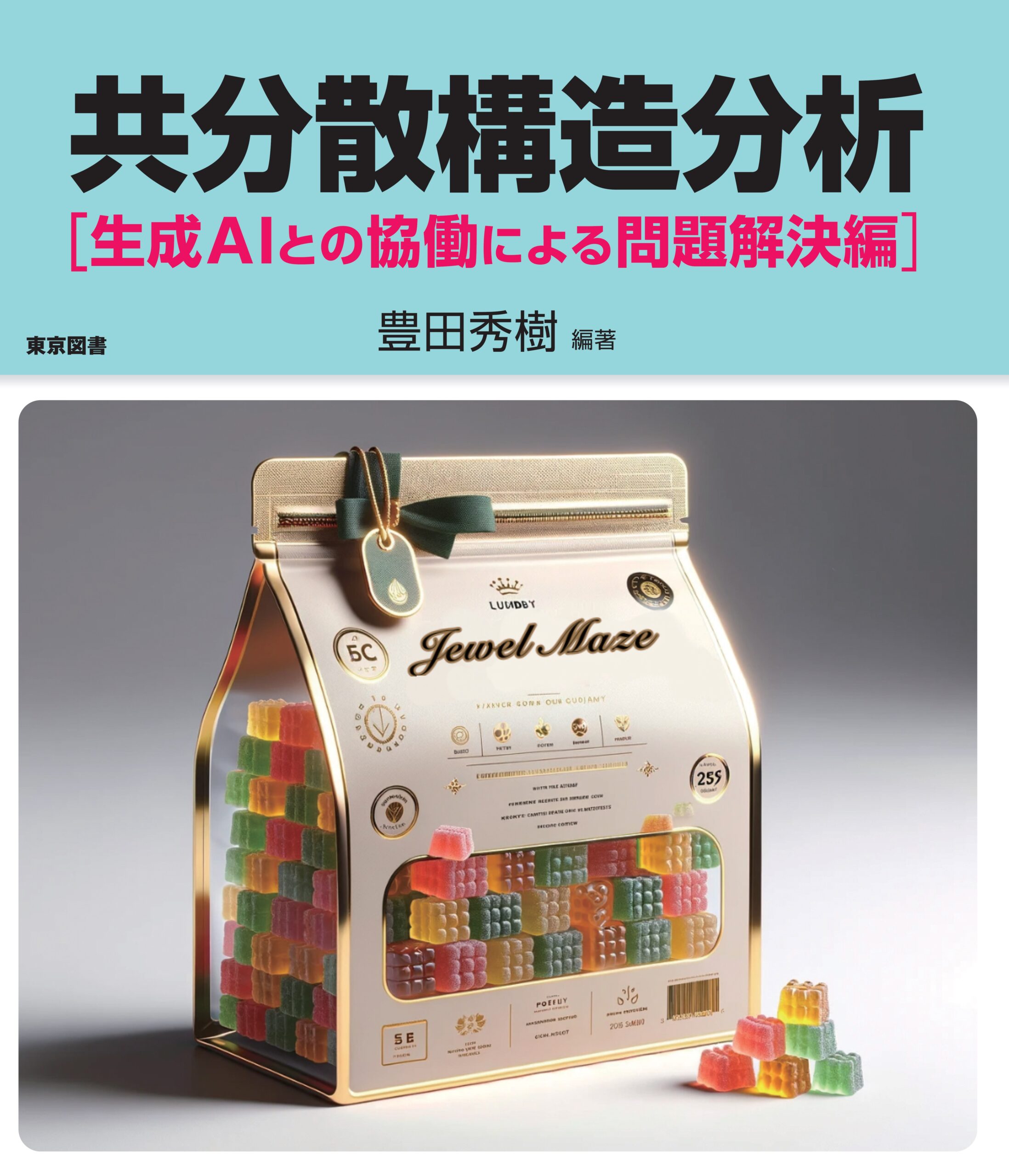
B5判変形 336頁 定価 3960 円
ISBN 978-4-489-02445-0 C0040
2025年7月刊行
◎生成AI とコラボレーションした、全く新しい共分散構造モデル!
編者等が開発した、全く新しいオリジナルの共分散構造モデルとして、新商品開発の文脈で、生成AI とコラボレーションしながら教程を展開する。新商品開発に代表される問題解決場面では、収束的思考と拡散的思考の両方が必要されるが、この一連の役割分担は、ChatGPT を始めとする生成AIが登場したことによって、コペルニクス的転回といっても過言でない程に変化した。この変化を、EPS、PCS、GAS、KMDという手法により、新しい共分散構造モデルとして詳細に解説する。
■編著者
豊田秀樹(とよだ ひでき)
1961年 東京都に生まれる。
1989年 東京大学大学院・教育学研究科(教育学博士)。
日本行動計量学会優秀賞(1995年)、
日本心理学会優秀論文賞(2002年、2005年)受賞。
イリノイ大学心理学部客員研究員などを経て、
現 在 早稲田大学文学学術院教授。
専門は心理統計学、マーケティングサイエンス。
研究の合間の映画鑑賞が無上の楽しみ。
◎主な著書(東京図書)
『共分散構造分析[Amos編]―構造方程式モデリング―』(編著)
『共分散構造分析[R編] ―構造方程式モデリング─』(編著)
『購買心理を読み解く統計学 ―実例で見る心理・調査データ解析28』
『データマイニング入門 ―Rで学ぶ最新データ解析─』(編著)
『検定力分析入門 ―Rで学ぶ最新データ解析─』(編著)
『回帰分析入門 ―Rで学ぶ最新データ解析─』(編著)
『因子分析入門 ―Rで学ぶ最新データ解析─』(編著)
『紙を使わないアンケート調査入門 ―卒業論文,高校生にも使える─』(編著)
『もうひとつの重回帰分析 ―予測変数を直交化する方法─』(編著)
『人工知能入門-初歩からGPT/画像生成AIまで-』(編著)
■著者
馬 景昊(早稲田大学大学院文学研究科)
佐々木研一(早稲田大学大学院文学研究科)
浅野懐星(早稲田大学大学院文学研究科)
御山孝誠(早稲田大学大学院文学研究科)
丹澤絢(早稲田大学大学院文学研究科)
信吉珠実(早稲田大学大学院文学研究科)
藤後玄徳(早稲田大学文学部)
大橋洸太郎(文教大学情報学部)
第1 章平均共分散構造分析入門
1.1 事例
1.2 統計学初歩
1.2.1 多変量データ
1.2.2 図による要約
1.2.3 平均
1.2.4 分散・SD
1.2.5 標準化
1.2.6 相関係数
1.2.7 確率変数の期待値・分散
1.2.8 データの関係性と構造モデル
1.3 測定方程式
1.3.1 広告展開前の観測変数の測定方程式
1.3.2 固定母数
1.3.3 広告展開後の観測変数の測定方程式
1.3.4 制約母数
1.3.5 測定方程式の行列表記
1.4 構造方程式
1.4.1 構成概念f2 の平均と分散
1.5 母数・変数
1.5.1 変数の分類
1.5.2 外生変数の平均・分散
1.5.3 共分散に関する補足
1.5.4 外生変数間の共分散
1.6 パス図
1.7 平均共分散構造
1.7.1 平均構造
1.7.2 共分散構造
1.8 母数の推定
1.8.1 多変量正規分布
1.8.2 最尤推定法
1.9 結果と解釈
1.9.1 広告は効果があったのか?
1.9.2 その他の母数の結果と解釈
1.10 新商品開発における共分散構造分析の活用
第2 章R 言語入門
2.1 R 言語基礎
2.1.1 R 言語速習
2.1.2 記述統計量
2.1.3 主要な統計量
2.1.4 まとめ1
2.2 OpenMx パッケージ
2.2.1 OpenMx の考え方
2.2.2 初期設定とデータ準備
2.2.3 モデル内で使用される各行列の定義
2.2.4 結果の出力と整形
2.2.5 まとめ2
第3 章共分散構造分析を用いた新商品開発
3.1 共分散構造分析を用いた新商品開発の手順
3.1.1 ポジショニングマップの作成
3.1.2 新商品のコンセプトの作成
3.1.3 新商品のブランド要素の決定
3.1.4 消費者のセグメンテーション
3.2 新商品開発におけるChatGPTの活用方法
3.2.1 ChatGPT の概要と特徴
3.2.2 ChatGPT を使用する際の注意点
3.2.3 ChatGPT の利用方法
3.2.4 プロンプトエンジニアリング
3.2.5 ChatGPT を活用した新商品開発の実践に向けて
3.3 新商品開発におけるGoogle フォームの活用
3.3.1 調査票の構成
3.3.2 Google フォームの概要と特徴
3.3.3 Google フォームの作成
3.4 コラム:フェルミ推定と新商品開発
3.4.1 規模の見積もり
3.4.2 フェルミ推定の概要
3.4.3 フェルミ推定の分類
3.4.4 実例:柔軟剤の年間国内市場規模
3.4.5 最後に
3.4.6 ドリル:「グミ」・「飲料水」
3.4.7 ドリルの解答例
第4 章EPS SEM による探索的ポジショニング分析
4.1 EPS で行うポジショニング分析
4.1.1 ポジショニング分析における属性の重要性
4.1.2 ポジショニングマップの作成
4.1.3 SD 法によるデータを用いたポジショニング分析
4.1.4 EPS と従来のポジショニング分析の違い
4.2 EPS の数理
4.2.1 EPS の観測変数ベクトル
4.2.2 EPS の測定方程式
4.2.3 EPS の構造方程式
4.2.4 EPS の平均構造
4.2.5 EPS の共分散構造
4.2.6 母数推定における制約
4.2.7 EPS のドリル
4.2.8 EPS のドリルの正解
4.3 EPS の適用例及びスクリプトの解説
4.3.1 ChatGPT を用いたポジショニングの属性抽出
4.3.2 形容詞対の選定とSD 法の導入
4.3.3 EPS によるポジショニング分析
4.3.4 EPS 関数の解説
4.4 課題
第5 章2 相データのポジショニング分析法
5.1 因子分析と商品開発
5.1.1 因子分析の枠組み
5.1.2 適応例:アイスクリーム知覚マップ
5.1.3 スクリプト解説
5.2 コレスポンデンス分析の概要
5.2.1 コレスポンデンス分析の枠組み
5.2.2 適応例:アイスクリーム知覚マップ
5.2.3 スクリプト解説
5.3 課題
第6 章コンジョイント分析
6.1 導入
6.1.1 コンジョイント分析の手順
6.2 要因と水準の選定:ChatGPTの活用
6.2.1 プロンプト例と技法
6.2.2 提案された内容の検討と要因・水準の決定
6.3 直交表の概要
6.3.1 直交表とは
6.3.2 直交表の基本原理
6.3.3 直交表を用いるメリットとデメリット
6.3.4 コンピューターによる直交表の作成
6.4 調査の実施
6.5 数理・適用例
6.5.1 回帰分析
6.5.2 重回帰分析
6.5.3 ダミー変数による重回帰モデル
6.5.4 データの成形
6.6 結果と解釈の指標
6.6.1 決定係数
6.6.2 部分効用値
6.6.3 相対重要度
6.6.4 プロファイルの総効用値
6.7 R スクリプト解説
6.7.1 準備
6.7.2 コンジョイント分析の実行
6.8 課題
第7 章ブラッドリー・テリーモデル
7.1 ブラッドリー・テリーモデル
7.1.1 ブラッドリー・テリーモデル(Bradley-Terry model) とは
7.1.2 ブラッドリー・テリーモデル(Bradley-Terry model) の数理
7.1.3 ブラッドリー・テリーモデルの適用例: 飲料商品の商品名の決定
7.1.4 ブラッドリー・テリーモデルのスクリプトの解説
7.1.5 課題
7.2 ダイナミック・ブラッドリー・テリーモデル
7.2.1 ダイナミック・ブラッドリー・テリーモデルとは
7.2.2 DBT モデルの数理
7.2.3 DBT モデルの適用例
7.2.4 DBT モデルのスクリプト
7.2.5 課題
第8 章PCS SEM による一対比較分析
8.1 シェッフェの一対比較法とPCS
8.2 PCS の数理
8.2.1 PCS における評価の差の表現
8.2.2 PCS の測定方程式
8.2.3 PCS の構造方程式
8.2.4 PCS の平均構造
8.2.5 PCS の共分散構造
8.2.6 母数推定における制約
8.2.7 PCS のドリル
8.2.8 PCS のドリルの正解
8.3 PCS の適用例及びスクリプトの解説
8.3.1 ChatGPT による商品名の候補の考案
8.3.2 適用例:グミの商品名の決定
8.3.3 PCS のプログラム
8.3.4 関数PCS の解説
8.4 課題
8.5 コラム:オリジナルAHP モデル
8.5.1 階層構造の構築
8.5.2 AHP の数理
8.5.3 適用例
8.5.4 スクリプトの使い方
8.5.5 AHP のドリル
8.5.6 課題
第9 章GAS(理論編)SEM による集団AHP
9.1 導入
9.1.1 AHP の復習
9.2 GAS の数理
9.2.1 GAS の必要性
9.2.2 集団における代替案と観点の評価
9.2.3 評価の散らばりに関する指標
9.2.4 個人の代替案の評価
9.2.5 個人の観点の評価
9.2.6 GAS における集団総合評価
9.2.7 個人の観点の評価
9.2.8 個人の代替案の総合評価
9.2.9 因子スコアやF を使った分析
9.2.10 追加の分析
9.3 GAS(理論編)のドリル
9.3.1 GAS(理論編)のドリルの正解
第10 章GAS(実践編)SEM による集団AHP
10.1 ChatGPT とGAS
10.1.1 ChatGPT から「観点」を決める
10.2 質問項目の説明
10.3 GAS のプログラム
10.4 GAS の結果と解釈
10.4.1 (1) 集団における観点別の代替案の評価
10.4.2 (2) 集団における観点の評価
10.4.3 (3) 集団における観点別の代替案の評価の散らばり
10.4.4 (4) 集団における観点の評価の散らばり
10.4.5 (5) 集団における代替案の総合評価
10.4.6 (6) 集団における代替案の総合評価の散らばり
10.4.7 (7) 個人の観点別の代替案の評価
10.4.8 (8) 個人の観点の評価
10.4.9 (9) 個人の代替案の総合評価
10.4.10 (10) 因子スコアやF を使った分析
10.4.11 (c) 集団の評価(zero sum)について
10.5 関数の説明
10.5.1 関数出力一覧
10.6 課題
第11 章KMDマハラノビス距離によるk-means 法
11.1 導入
11.1.1 k-means 法によるクラスター分析
11.1.2 KMD によるクラスター分析
11.1.3 マーケティング分野への有効性
11.2 数理
11.2.1 KMD のアルゴリズム
11.3 KMD の適用例及びスクリプトの解説
11.3.1 KMD 分析の準備
11.3.2 KMD 関数の実行
11.3.3 分析結果の考察
11.4 課題
11.5 コラム:PSM(価格感度測定)
11.5.1 新商品開発における価格決定の重要性
11.5.2 価格感度を測定する4 つの質問
11.5.3 調査票と価格感度データ
11.5.4 累積比率表とその読み取り
11.5.5 分析結果
11.5.6 価格設定における重要な5 つの指標
11.5.7 R スクリプト解説
11.5.8 ドリル「柔軟剤」
付章A 線形代数
A.1 行列
A.1.1 行列の定義
A.2 行列・ベクトル・スカラーの演算
A.3 トレース,内積・ノルム,直交行列,行列式
A.4 逆行列,平方根行列
A.5 クロネッカー積,ベック作用素とアダマール積
A.6 固有値と固有ベクトル
A.7 統計学に使われる行列
付章B ChatGPT とGoogle フォーム
B.1 ChatGPT のアカウントの作成方法
B.1.1 ChatGPT への登録方法
B.1.2 ChatGPT のアップグレード
B.2 Google フォーム
B.2.1 Google アカウントの作成
B.2.2 その他の回答形式
B.2.3 その他のフォームの送信方法
本書で使用している各データを、こちらからダウンロードすることができます。
【注意】
- ファイルは、通常の運用に関してはなんら問題のないことを確認していますが、運用はすべて自己責任で行うものとします。
- 運用の結果、万一損害が発生したとしても、著者および出版社はいかなる責任も負いません。
- サービスの供与などを行うことは固く禁じます。
